皆さん、こんにちは。
東京都西東京市を拠点に、関東一円で一般住宅から集合住宅、ビル、店舗、公共建築などの内装左官・外装左官を手掛けている武蔵組です。
「左官職人になりたいけれども、仕事がキツイって本当?」という相談をよく受けます。
たしかに左官の仕事はデスクワークなどとは違い、体を動かす仕事なので、ラクと言っては正しくないかもしれません。しかし一般的に思われているほどキツイわけではないのも事実。
そもそも、働くうえで100%ラクな職業などありませんし、左官はとてもやりがいのある仕事です。今回は左官職人の仕事について、大変だと思われることや、やっていてよかったと思えること、ぜんぶ率直にご紹介します!
■左官がキツイと思われている理由とは?

左官がキツイと言われる理由の一つに、工期が厳しくなりがち、ということが挙げられます。というのも、左官が担うのは、仕上げの工程。
大工が柱や梁など建物の骨を組み上げて、内部の造作や仕上げが始まる段階で現場に入るため、ほかの職人が仕事を終えないと自分の作業を始められません。
天候不順や人不足など、往往にして現場のスケジュールは遅れがちなので、左官にしわ寄せがきてしまいます。
基本的に工期を伸ばすことはできないので、全体の作業が遅れた分、左官など仕上げを担うスペシャリストたちが頑張らなければなりません。
また基本的に建築の現場では電気が通っておらず、設備は最後に取り付けられるので、快適な空調は期待できません。リノベーションやリフォームの現場でも、基本的に漆喰やモルタルなどの左官材の素材は水分が減ると作業性が悪くなるため、空調を入れないのが一般的。
このため、左官は真夏も冬も空調を効かせられない環境下で作業をしなければなりません。
また、左官は練り上げた材料を鏝(こて)に載せて壁などに塗り広げる動作を繰り返します。水分を含んだ土は重いので、それなりに体力が求められます。
■左官に向いていない人ってどんなタイプ?

したがって、体力に自信がないという人は、あまり左官向きとは言えません。
左官といえば鏝で左官材を塗る作業を思い浮かべがちですが、ブロックを積んだりセメントを運ぶような力仕事も必要です。
また一つのことに情熱をもって集中できない人も、左官向きではないと言えます。
好奇心旺盛なのは良いことですが、左官は長い歴史をもつ奥深い世界なので、一つの技術を探究してゆくことが求められます。
また左官の道に入ってしばらくは、同じ作業を繰り返すことで技術を習得します。
興味の対象が広く浅く長続きしないタイプですと、左官の醍醐味を知る前に飽きてしまうかもしれませんね。
■左官職人に向いているのはこんな人!

では、どんなタイプの人が左官に適正あり!と言えるのでしょう。
まずは伝統的なものに興味がある人。
左官は、脈々と受け継がれてきた日本の伝統技術です。歴史的な建造物の修復はもちろん、今でもスタイリッシュな住宅やおしゃれなホテルに左官が使われるなど、現代建築に欠かせません。
そして歴史が長いだけに、左官ではさまざまな技法が編み出されてきました。左官は日本の知恵と技術が結集した世界に誇る技術なのです。
そして、技術を身につけたいと考えている人に左官はうってつけ。知れば知るほど左官の世界に魅了されます。
コツコツと根気よく努力できる人や、ていねいな仕事がしたい、という人。そして仕上がりの美しさや精密さにこだわりがある人や、自分の仕事にプライドをもちたい人にとって、左官は天職と言えるでしょう。
■良い左官職人になるためにはどんなスキルがあるとよい?
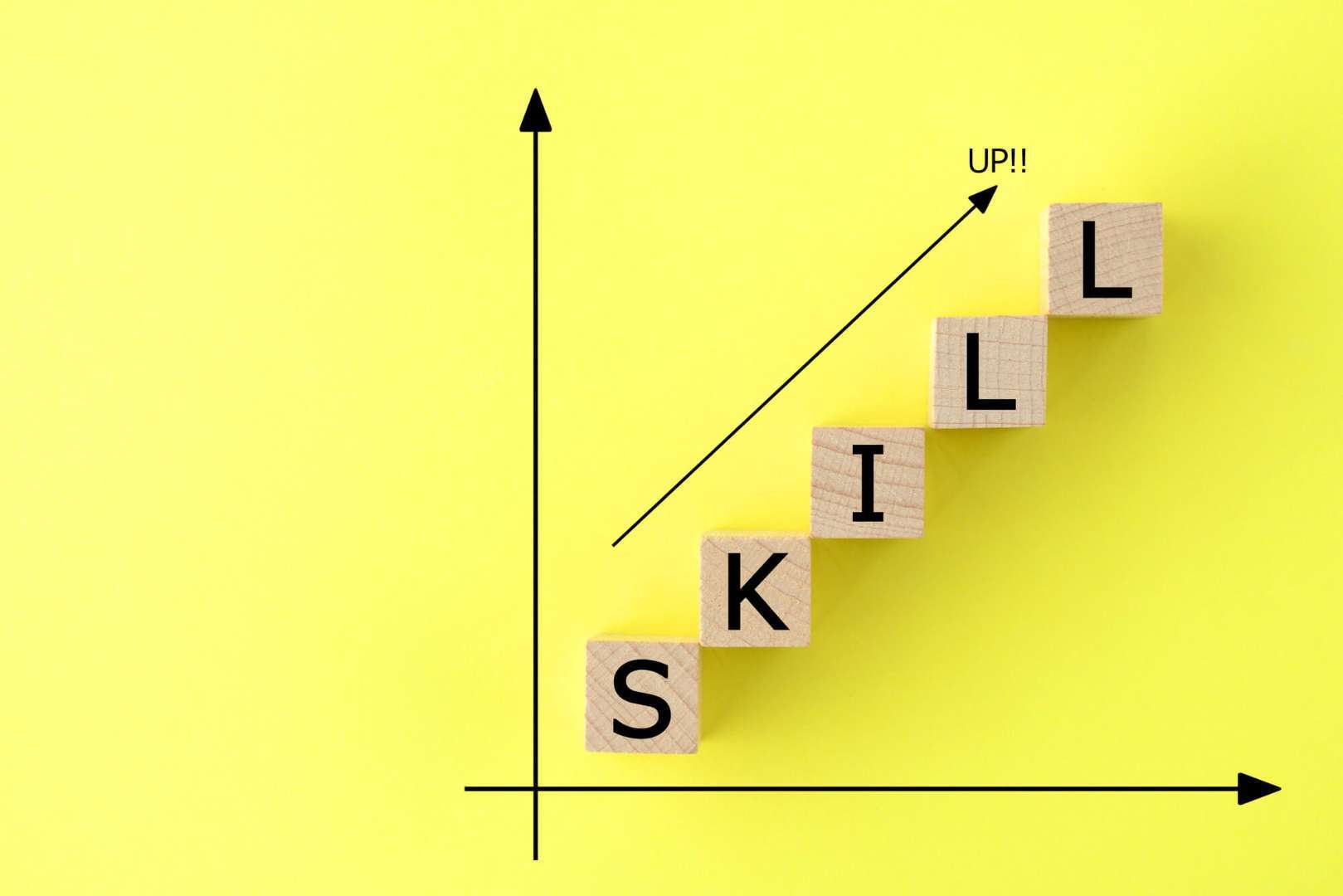
左官に必要なのは、観察眼です。
後輩や未経験者の指導にすぐれた左官会社では、コツを上手に教えてくれるものですが、ただ言われたことをその通りにやっているだけでは、技術は向上しません。
現場で場数をこなし、さまざまな経験を経ながら左官職人はスキルアップしていきます。
また左官材料の調合は、季節や種類に応じては、肌感覚で水分量を調整することが求められます。ベテランの先輩ならこんな時どうしていたか、その都度、これまで培ってきた観察眼が問われるものです。
歴史への興味の深さも左官技術を左右するうえで重要。ただし、日本史を勉強し直したほうがよい、と言っているわけではないので、そこは安心ください。
左官はご紹介した通り、日本の風土が育んだ伝統技術です。
その土地で採れる土を使い、気候風土に応じて地域独自の技術が生まれてきました。
たとえば瓦と漆喰でつくられる「海鼠壁(なまこかべ)」。武家屋敷などでも用いられているますが、漆喰でがっちりと瓦を固めるため、台風被害が多い四国や瀬戸内地方でよく見られます。
台風銀座とも呼ばれ大雨の多い高知では、一般的な漆喰のように糊を入れず、藁スサを発酵させることで水に強い特性をもたせた「土佐漆喰」が生まれました。
滋賀の大津を発祥とする「大津壁(おおつかべ)」は、この地で得られる良質な白土をもとにした土壁で、鏝で何回も押さえることでツヤを放つほどのキメの細かさが魅力。またひと口に大津壁と言っても、「泥大津」「並大津」「大津磨き」とグレードが異なり、最高級の「大津磨き」は土壁なのにまるで鏡のように光ります。「並大津」は黄色や赤など鮮やかな色がポピュラー。「泥大津」は、泥色の土や田んぼの土などに石灰を混入した材料を塗りつけた、強度の高いタイプです。
一方、加賀百万石・金沢ではビビッドな加賀群青の土壁(じゅらく壁)が有名です。金沢で高貴な色といえば、青。前田家第十三代当主がつくらせた国宝「成巽閣(せいそんかく)」では鮮やかな瑠璃色の天然鉱石・ラピスラズリが左官壁に使われています。
土の層が美しいグラデーションを織り成す技術を「版築(はんちく)」と呼びます。土を一層ずつ突き固めることで独特の風合いが得られ、日本では古墳時代から用いられてきました。有名どころでは法隆寺、今でもホテルやモダンな住宅のエントランスなどに使われています。
このように左官は色も工法もテクスチュアもさまざま。歴史や風土とのかかわりを知るほど、その魅力に引き込まれることでしょう。
■奥深い左官の世界でスキルアップ! 武蔵組は未経験者も、経験者も大歓迎です
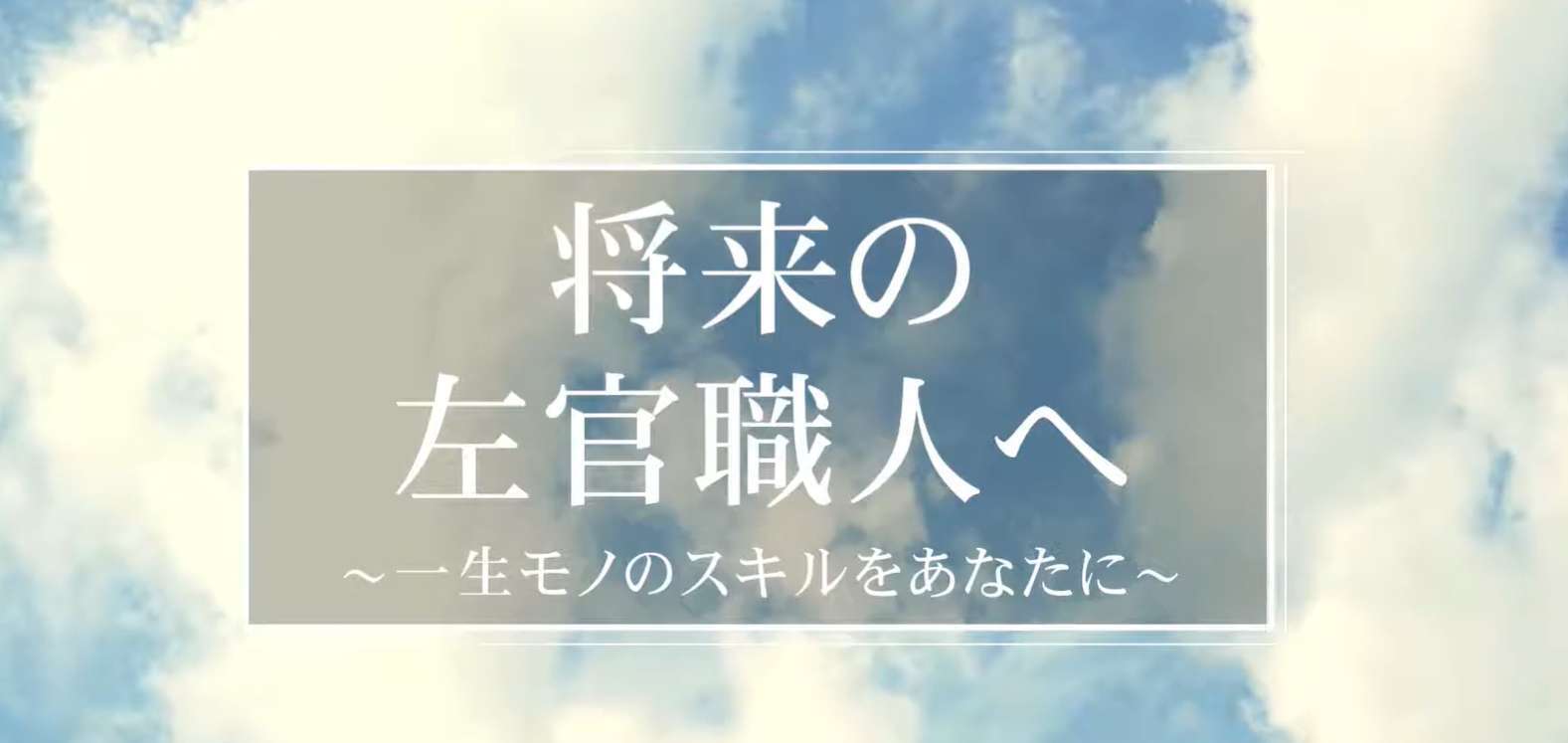
左官の大変な面も紹介しましたが、建築の現場ならどの職種でも変わりありません。
むしろ、鳶や大工のように鉄骨の足場を組んだり柱・梁のような構造材を運ぶこともなく、こうした仕事に比べれば体力的なハードルや危険度は低いと言えるでしょう。
最近ではチャットボット「Chat GPT」が話題で、レポートや卒業論文まで書けてしまうとか、絵心がないのにも関わらずAIを使えば1分でリアルな絵が描けるなど、デジタル技術が見違えるように発達しています。こうした進化の一方で、イラストレーターや文筆業に従事している人が、仕事を奪われるという危惧の声も上がっています。
一方で、左官はどれほどコンピュータ技術が発達しても、真似できるものではありません。こうした技術を身につけていれば一生を通じて働くことができ、最近では職人に対するニーズが高くなっています。(https://www.m-s-g.jp/blog/column/154555)
左官のプロ集団である武蔵組は現在、左官職人を募集しています。
未経験だけれども左官職人になりたい!といった方や、良い現場を経験して左官をもっと深く知りたいという方は大歓迎。
入社してから職人として独立するまで一貫してサポートいたします。
くわしくは募集要項をご覧ください!


